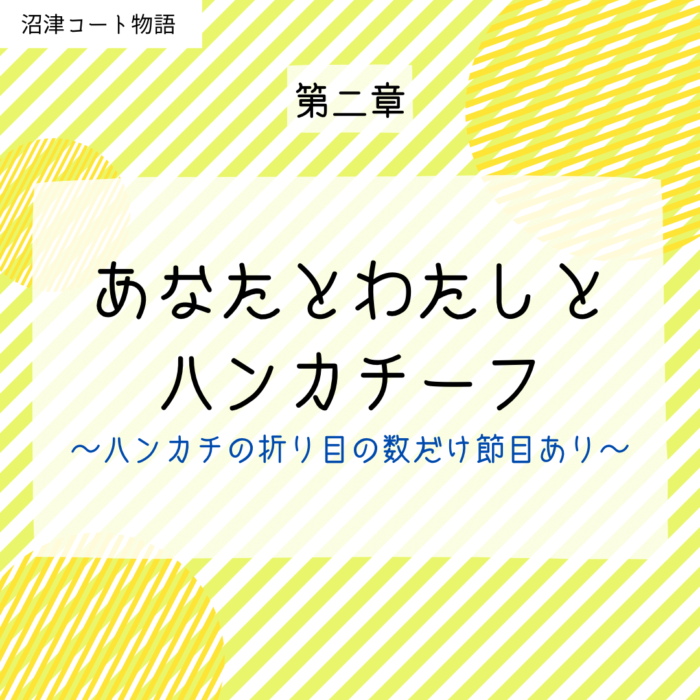
「あなたとわたしとハンカチーフ」
~ハンカチの折り目の数だけ節目あり~
第二章
ーあなたに貰ったハンカチで、涙を拭いたー
——————————
1986年。
騒ぎ、歌い、飲み明かす人々が街にあふれ、日本がバブルに突入したこの年。
羊介と麻子はあれからほどなく、当たり前のように交際をスタートした。
金曜の夜、ボディコンに身を包みディスコへ繰り出す同僚たちを尻目に、麻子はお気に入りのリネンのシャツを身に纏い、きちんと上までボタンをとめると、流行りのネコのキーホルダーがついた小さなポシェットを肩にかけ、ネオンまたたく街とは反対の方向へと、足を進めていた。
最近買った、写ルンルンですを初めて使う時が来た。
数日前、彼が「次に会うときには、大事な話がある。」と言ったからだ。
記念の日をおさめるべく、それをポシェットに忍ばせていた。
午後6時。
さっきまで降っていた雨がコンクリートに染み込んで、蒸し蒸しとする暑さがこみ上げていた。
二人の行きつけのこの店は、大通りに面したビルの一階にあり、重厚感のある扉を開けると、そこにはすでに彼の姿があった。

ハンカチで拭っている額の汗は、いつにも増して多く浮かんでいるように見えた。
麻子は、席につくと彼に微笑んだ。
「待った?今日も早いのね。」
彼はいつも、「ちょうどいま来たばかりだよ。」と言う。
グラスの水滴が、磨かれたテーブルのあちこちに輪っかをつくっていた。
真っ白な皿にのったナポリタンと、コーヒー。いつもの味を、いつものようにふたりで頬張った。

ただ、いつもと違うのは、彼のそのブラックコーヒーにも似た瞳が、なかなかこちらを見てくれないこと。
ひとしきり、一週間の出来事を報告し終えると、ふたりの間にはしばし沈黙が流れていた。
小さな振り子時計が鈍い音で、ゴーンと20時を告げる。麻子は、そんな沈黙でさえも愛おしかった。
いまこの瞬間を、大事にしたい。
彼がその重い口を開くのを待っていた。
——————————
2年前の6月のあの日ーー。
麻子は、趣味の喫茶店めぐりで、海と山が広がる街、沼津を訪れていた。都心から少し足を伸ばして気分転換するには、もってこいの場所であった。
そして、そこに住む人々は皆やさしく、穏やかであった。
千本松原を散歩し、海風に当たりながら幼いこどもが走り回る様子に、頬がほころぶ。
その日、麻子はいくつか喫茶店をめぐり、ほくほくとした様子で帰路につこうとしていた。
そんな時に、あの土砂降りにあったのだ。
傘をもっておらず、最後の最後にツイテナイなぁと思っていた。
必死にバス停まで走る。強い雨に前が霞む。
顔にかかった滴を振り払うと同時に、何かに勢いよくぶつかった。
大きな背中が目の前に来たかと思うと、振り返った彼の、すこし驚いた顔が、みるみる赤くなっていき、まるで熟れたコーヒーの実のようだと思った。
そして、気づいた。
「すべてが、この人と出会うためだったんだ」と。
——————————
そんなことを思い出しながら、麻子は静かに微笑み、羊介を見つめる。
ふいに、羊介が意を決したようにこちらを見た。
もうすでにそこをつきかけている、コーヒーを口に含むと、
彼は顔を真っ赤にしながら呟いた。
あのときと同じ、熟れたコーヒーの実のように。
「あの、ぼ、ぼ、ぼくと。け…………」
「え、なに? 聞こえないよ?」
彼は立ち上がると、店内に響き渡るほどの声で言い放った。
「ぼくと、結婚してください!」
麻子の頬に一筋、甘い涙がつたう。
そして小さく、強く、答えた。
「はい。」
店のマスターが、やれやれといった具合に、コーヒーを煎れ終えていた。
ふたりの前にそっと、「サービスだよ。」と言って、熱々のコーヒーが置かれた。
「角砂糖は、今日はひとつで充分かな?」
いつもは二つ。
甘いのがすきな麻子だが、なぜだかいつもより甘く感じるコーヒーを飲みながら、小さなポシェットに忍ばせておいた写ルンルンですを取り出すと、羊介に向けて、満足げにシャッターを切った。

→第三章へつづく
——————————–
撮影協力:
芦澤有里
ロケ地:
欧蘭陀館 香貫店